Episode 03:すべてを変えた車 ― AE86
イニシャルDとの出会い
僕と AE86 との最初の出会いは、まだ高校生の頃だった。週刊ヤングマガジンで連載されていた漫画『イニシャルD』を読んだのがきっかけだ。 山道を駆け抜ける 1 台の古いハチロク。主人公・藤原拓海が、父親の豆腐屋の配達で鍛えた運転技術を武器に、愛車 TOYOTA SPRINTER TRUENO AE86 で数々のライバルと戦っていく物語。 当時の僕にとって、あの漫画はただの「クルマ漫画」ではなかった。夜明け前の峠道、エンジン音とタイヤのスキール音だけが響く世界。そこには、狭い日常から抜け出していく「自由」と「自分だけの場所」があった。 「いつか自分も、ハチロクで走りたい。」 その気持ちは、心のどこかにずっと居座り続けることになる。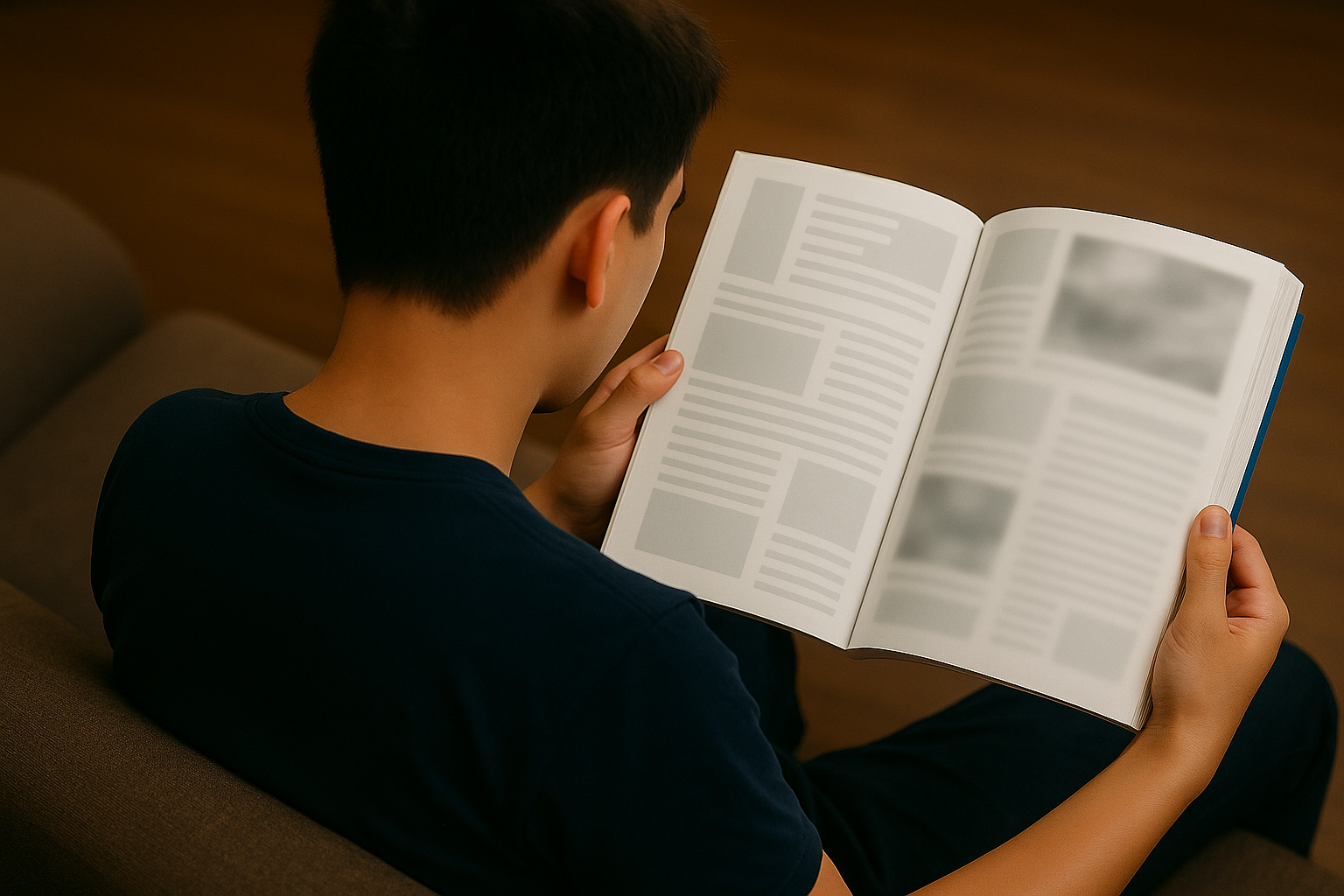
『イニシャルD』に出会った頃の空気。
免許を取るために学校をサボった日々
18 歳になれば車の免許が取れる。そのことを知ってから、僕のゴールはずっと「18 歳の誕生日」だった。 少しでも早くハンドルを握りたくて、誕生日の前から自動車教習所に通い始めた。ときには高校を休んでまで教習所へ向かったこともある。 今思えば、先生や親から見たら褒められたことではなかっただろう。けれど当時の僕にとっては、それよりも「1 日でも早くクルマを運転したい」という気持ちの方が圧倒的に大きかった。 ようやく免許を手にしたとき、あの薄いプラスチックカードが「世界の広さ」そのものに見えた。
免許に手を伸ばしていた頃。
最初の相棒は、母のスズキ・アルト
とはいえ、免許を取ったからといって、すぐに自分のクルマが買えるわけではない。高校を卒業したばかりの自分には、そんなお金はどこにもなかった。 しばらくのあいだ、僕は母が乗っていた スズキ・アルト(4速MT) を借りて運転していた。 小さなエンジンに軽いボディ。ギアをつなぐたび、クルマは僕の操作に素直に反応してくれる。パワーはない。それでも「運転するってこんなに楽しいんだ」と教えてくれたのは、あのアルトだった。 ハチロクではなかったけれど、あの頃の僕はアルトのフロントガラス越しに、いつか手に入れる AE86 の姿を重ねていたのかもしれない。
最初の相棒は、母のアルト。
新聞配達とコンビニのバイトを掛け持ちした理由
どうしても AE86 が欲しかった。そのために僕が選んだ方法は、とにかく働くことだった。 朝は新聞配達。暗い街を原付バイクで走り、ポストへ新聞を投げ込む。昼は学校。夜はコンビニのバイト。 遊びに行く余裕なんてほとんどなかった。それでも「ハチロクを買う」という目標だけは、どんな眠気よりも強かった。 そして、少しずつ通帳の残高が増えていった。コツコツ貯めたお金が 60 万円 に到達したとき、「ついに本気で探せる」と実感した。
朝の新聞配達。
毎日磨いて、毎日乗った日々
気がつけば AE86 は、ただの移動手段ではなく、家族であり、親友であり、自分の分身のような存在になっていた。 走ることと、夢を見ること。その両方を教えてくれたのが、あの 1 台の AE86 だった。次のエピソード → Episode 04



コメント